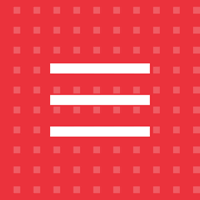園や学校への行き渋り・・・原因には、病気や特性が関係している場合もあります。
朝なかなか起きられず、倦怠感や頭痛に悩まされ、次第に遅刻が増えて登園できなくなったり、不登校になったり。
その背後には「起立性調節障害」が潜んでいることもあります。
家庭でどのように対応し、園や学校にはどのような配慮を求めるべきなのか。
東京逓信病院小児科で起立性調節障害の専門外来を担当する中澤聡子医師に話を伺いました。
(※2025年1月21日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
起立性調節障害への正しい理解と早めの対応が大切
起立性調節障害は、午後には元気になることが多いため、「やる気がないのでは?」「学校に行きたくないだけ?」と思われがちですが、これは自律神経の機能不全による病気です。
朝起きられない、朝礼や入浴時に気分が悪くなる、頭痛や腹痛、動悸、食欲不振、倦怠感など、症状はさまざまです。
成長に伴う自律神経やホルモンの変化によってバランスが崩れ、発症することがあります。
主に小学校高学年から思春期にかけて多く見られますが、低学年のうちに朝礼で倒れ、診断を受けるケースもあります。
中学生の約1割が発症するとされ、生活習慣やストレスが大きく影響します。
予防や症状の軽減には、規則正しい生活が不可欠です。
決まった時間に就寝・起床し、3食しっかり食べること、水分と適度な塩分を十分に摂取して血液量を維持することが重要です。
また、適度な運動で筋力をつけ、血流を良くすることで、脳や上半身への血流低下を防ぐことも大切です。
早めの診断と理解がカギ。起立性調節障害の対処法
外来では、まず詳しく話を聞いたうえで、ほかの病気の可能性を検査し、異常がなければ「新起立試験」で血圧や脈拍数を測定し、問題の有無を診断します。
その後、生活習慣の改善について指導し、必要に応じて薬を処方することもあります。
親子で病気のメカニズムをしっかり理解し、生活習慣を整え、ストレスの原因を取り除くことで、驚くほど早く回復するケースもあります。
しかし、人間関係の問題が先にあり、それが原因で登校できず体を動かさなくなった結果、発症する場合もあります。
また、発症後につらい症状があっても、周囲の理解が得られずストレスが増し、長引いてしまうことも少なくありません。
友人関係が希薄になると、ますます登校しづらくなるため、早めの対応が重要です。
神経発達症の子どもへの理解と学校のサポートの大切さ
神経発達症(発達障がい)のある子どもが起立性調節障害を発症するケースも増えています。
必要に応じて、学校に配慮を求めることも検討しましょう。診断書の発行が可能な場合もあります。
学校には、頻繁な遅刻や欠席の背景にある要因を説明し、本人が改善しようと努力していることを伝えることが大切です。
そのうえで、子どもが無理なく学校生活を送れるよう、適切な配慮をお願いしましょう。
進級や受験時の配慮と、周囲の理解の重要性
少し先の話になりますが、高校の進級に関する相談は特に多く寄せられます。
出席日数が足りないことを理由に、中高一貫校で高校へ進めないケースや、高校で留年となるケースもあります。
ただし、診断書を提出することで、柔軟な対応を受けられる場合もあるようです。
また、大学入学共通テストなどの試験においても、会場や座席の配置、飲み物や薬の置き場所などの配慮を受けられることがあります。
必要な支援を受けるためにも、事前に確認しておくことが大切です。
家庭環境の変化により、親子や祖父母との関係が子どもに影響を与えることもあります。
家庭で気づくことが難しい場合は、学校の先生が異変を察知し、小中学生のうちに医療機関につなげることが重要です。
遅刻や欠席を責めるのではなく、周囲の理解を深めることで救われる子どもは必ずいます。