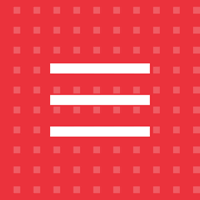仕事に家事に育児にと、毎日が忙しくて、まとまった勉強時間がなかなか取れない…そんな方も多いのではないでしょうか?
でも、そんなみなさんこそ「スキマ時間」を上手に活用すれば、保育士試験の合格がぐっと近くなります。
ここでは、忙しい方にこそおすすめしたい「スキマ時間活用法」をご紹介します。
1. 朝の10分を見直そう!「ながら勉強」で知識を定着
朝は1日の中でも特に集中力が高まりやすく、記憶の定着にも効果的なゴールデンタイム。
「でも、朝は子どもの支度や自分の出勤準備でバタバタ…」という方でも、実は“ながら勉強”で時間を有効活用できます。
たとえば、朝食の準備をしながら保育士試験の解説音声を流したり、洗顔や歯みがき中にキーワードを見返すだけでも立派な学習。音声アプリや単語カードアプリなど、視覚や聴覚を使ってインプットできるツールを味方につけましょう。
短時間でも毎日続けることで、知識は確実に積み上がっていきます。
2. 通勤・通学中もチャンス!耳から学ぶ習慣を
電車やバスでの移動、あるいは車を運転している時間も、立派な学習タイムに変わります。
ただスマホを見たり音楽を聞いたりしている時間を、「耳で学ぶ時間」に変えるだけで、1日の中に30分~1時間もの勉強時間になるのです。
おススメなのは、保育士試験に対応した音声教材や解説付きのポッドキャスト。繰り返し聞くことで記憶が定着し、用語や考え方が自然と頭に入ってきます。
特に苦手分野は耳で繰り返し聞くと、無理なく克服できることが多いです。
3. スマホを味方に!5分でできる小テスト習慣
スマホは今や、スキマ時間の強い味方。ちょっとした待ち時間や休憩中に、一問一答アプリや過去問アプリを開くだけで、効率よく知識の確認ができます。1回たった5分の学習でも、1日に数回繰り返せばかなりの量に。
ポイントは「今日は保育原理の分野だけ」「今日は施設分野だけ」など、テーマをしぼって取り組むこと。漠然と問題を解くよりも、意識的に学ぶことで記憶への定着率がぐんとアップします。
4. 家事中にもチャンスあり!目と耳を同時に使う
掃除や洗濯、食器洗いなど、家事の時間も実は「ながら勉強」にぴったりの時間です。手は動いていても、目や耳が空いている時間を活用すれば、無理なく知識を吸収できます。
たとえば、スマホに音声教材をダウンロードしておけば、洗濯物を干しながらでも保育所保育指針の内容を耳からインプット可能。さらに、「家事のこのタイミングではこれを聞く」とルーティン化することで、勉強が習慣化しやすくなります。
5. 1日5分の「ふり返りタイム」を作る
寝る前の数分間は、1日を振り返るのにぴったりの時間帯。その日の勉強内容をもう一度ざっと思い出したり、気になった点をメモに書き出したりするだけでも、記憶の定着に大きな効果があります。
「今日は何を学んだか」「どこがわからなかったか」を1行でもいいのでノートに書いてみましょう。
この小さな習慣を続けることで、自分の理解度や進捗を把握しやすくなり、学習へのモチベーションも上がるだけでなく、本番直前の“自分専用まとめ集”としても活用できます。