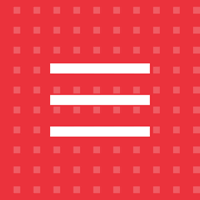世界各地の紛争地域で平和の維持に尽力する方々や、戦争の記録を通じて歴史の教訓を後世に伝える役割を担う方々がいらっしゃいます。現在、どのような思いでそのような活動に取り組んでいるのでしょうか。また、子どもたちに戦争について伝える際には、どのような視点を持つべきかについて、貴重なヒントをお伺いしました。
(※2024年8月4日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
平和への希望を胸に、苦しみに寄り添う対話を
国連事務次長・軍縮担当上級代表 中満泉氏より
ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエルのガザ地区への攻撃など、世界各地で戦争が絶えない状況が続いています。このような中で、私たちは未来を担う子どもたちにどのような世界を残せるのでしょうか。国際連合事務次長であり、軍縮担当上級代表の中満泉氏は、「決して希望を捨ててはなりません」と強く訴えています。
平和への道を探る。次世代に希望をつなぐために
21世紀にこのような悲惨な出来事が起きるとは、私たち自身も予想しておりませんでした。国連職員として、無力さを感じる瞬間があり、時には歯がゆさを通り越して怒りに似た感情が込み上げることもございます。現場では、命の危険と隣り合わせで活動を続けている同僚も多く、私自身も大きな苦しみを抱えています。
20代の娘たちからは、「こんな残酷な世界を、そのまま私たちに引き継がせないでほしい」との声を頻繁に聞きます。そのような声を受け止め、時間がかかるとしても、解決策を模索し続ける必要があると痛感しております。
現在、日本や世界では、社会のさまざまな場面で不平等や不公平が横たわっています。それらをどのように変えていくべきか、私たちの生活に結びつけて考えることから、平和の基盤が築かれるのではないかと考えております。
戦争については、ただ理解するだけでなく、「衝撃を受ける」ことも重要です。私自身、小学校4年生のときに訪れた長崎の原爆資料館で見た展示物、特に子どもたちの焼けただれた体の写真が、今でも鮮烈な記憶として残っています。それは恐怖であり衝撃であり、同時に「この世界でこんなことが二度とあってはならない」と深く心に刻まれた瞬間でした。
ただし、こうした体験においては、心のケアが重要であり、ただ「触れるだけ」で終わらせるのではなく、その後に大人や先生がしっかりと対話を重ねることが不可欠です。
さらに、小さな頃から、地理的に離れた場所であっても、自分たちと同じ世代の子どもたちが戦争で苦しんでいることを知る機会がなければ、大人になってからもその苦しみに心を寄せることは難しいのではないかと感じています。
思いやりの心で未来を変える、子どもたちへの責任と希望
例えば、街でホームレスの方を見かけたときに、「汚いから嫌だ」と避けるような子どもに育つのか、それとも「なぜこの方がホームレスになったのだろう」と考え、自分にできることを模索する子どもに育つのか。それは、周囲の大人たちの価値観や考え方に大きく左右されるのではないでしょうか。
「心を寄せる」ということは、単に同情するだけでなく、その人が望む生活を再び取り戻せるように何ができるかを考えることだと思います。特に子どもを育てる親や保護者には、大きな責任があります。誰も取り残されることなく、全員が幸せになる社会を目指して、そのための「思考の種」を子どもたちに植え付けることが、子育ての意義のひとつではないでしょうか。私は、どんな状況でも決して諦めてはならないと強く信じています。
人が変わることで、社会も少しずつ変化していきます。歴史を振り返れば、200年前には奴隷貿易が合法的な経済活動とされていました。その後、奴隷貿易の廃止を経て、戦時における非人道的行為を制限する国際人道法が整備され、さらに人権を基盤とした法律が進展してきました。このように、人類社会は長い視点で見れば確実に進歩してきたのです。そして、私たちはその歩みをさらに進めていかなければなりません。
社会の制度設計は、最も弱い立場にある人を中心に考えるべきです。なぜなら、強い立場の人々は自分たちで工夫し、問題を乗り越えていく力を持っているからです。
これからどのような社会を築いていくのかを対話し、将来的には子どもたち一人ひとりがその考えを行動に移していくことが重要です。それこそが、未来をより良いものにする第一歩になるのではないでしょうか。
戦争の記憶と子どもたち-理解を深めるための年齢と背景
アウシュビッツ公認ガイド・中谷剛氏より
ナチス・ドイツによる「アウシュビッツ強制収容所」では、ユダヤ人をはじめ約110万人もの命が奪われました。この場所を訪れる人々は世界中に広がっていますが、14歳未満の子どもの入場は推奨されていません。戦争の歴史を子どもたちが学ぶことについて、どのように考えるべきなのでしょうか。強制収容所内の博物館で20年以上ガイドとして働く中谷剛氏にお話を伺いました。
歴史の教訓を未来に・・・子どもたちと向き合う年齢と理解の深さ
14歳を基準とする理由には、子どもたちに過度なショックを与えないための配慮に加え、この場所で起きた出来事を十分に理解するには難しい年齢であることも関係しているのではないでしょうか。
ポーランドでは高校2年生で第二次世界大戦について学びます。それ以前に訪問するのは早すぎるとの考えが背景にあるのでしょう。
私個人の意見ですが、幼い子どもたちは、肌の色や宗教、政治、文化の違いを理由に友人を選ぶことは少なく、仲良くなるのも早い傾向があります。しかし、こうした心の壁が低い幼い時期には、アウシュビッツで起きたことを本質的に理解するのは難しいと思います。
「ここで何人がどのように命を落としたのか」を伝えることは可能ですが、それだけでは十分ではありません。アウシュビッツの博物館は、「二度と繰り返してはいけない」という教訓を伝える場です。この場所の背景には、人種差別、民族差別、障害者や性的少数者への差別といった問題が存在していました。これらを理解するには、他者との競争が始まり、自我が芽生え、自分と他人の違いを意識し始める年齢に達している必要があると感じます。
また、子どもたちは多くの場合、自分で選択する自由がありません。そのため、大人がより慎重に考え、適切な判断を下す責任があると思います。
私たちガイドの役割は歴史を伝えることです。しかし、それは「こうすれば悲劇が起きない」と教えることではなく、どうすればよいのかを考えるための材料を提供することだと考えています。
すべての人が自ら考え、行動することが求められています。そのため、伝える内容は誰にでも心を開いてもらえるよう工夫を重ねる必要があります。毎回少しずつ方法を変えながら、より良い伝え方を模索し続けています。
正解のない問いに向き合う。次世代への責任と希望
ここ数年、ウクライナ侵攻やガザでの戦闘など、心を揺さぶる出来事が続いています。そのたびに、記者として、そして一市民として自分に何ができるかを考え、行動してきましたが、思うように役に立てない無力感を抱える日々がありました。それでも、戦闘そのものを止めることはできなくても、自分の方法で社会に貢献しようと尽力される方々との取材を通じ、私自身が勇気をいただきました。
次の世代を担う子どもたちに、どのような社会を引き継ぐべきか。過去の戦争からどのような教訓を得られるのか。中満さんや中谷さんの言葉を通じて、「大人として果たすべき責任」の重さを改めて感じています。
このような正解のない問いに向き合い、考え続けることが必要です。読者の皆さまや識者の方々とともに、これからも答えを模索し続けていきたいと思います。